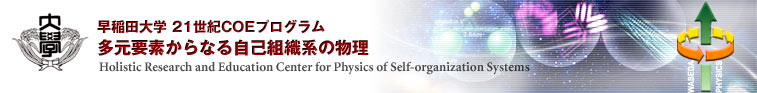‖研究テーマ‖科学技術の最先端に迫る‖研究概要‖多元要素からなる自己組織系とは、異種のユニットが相互作用することにより、自発的に構造や機能を獲得するシステムのことでその典型例は生物・生命現象に見られる。たとえば、生物を構成するDNAや蛋白質は、それぞれ4種類の塩基と20 種類のアミノ酸という多元要素からなる自己組織系である。生物以外にも、多元要素からなる自己組織系は物理学が対象と する様々な階層に現れる。たとえば高温超伝導体のような複雑な物性を示す固体では、電荷とスピンが自己組織化することが わかってきた。また、宇宙には星だけでなく暗黒物質やエネルギーが充満しているため、銀河分布は宇宙全体に均一ではなく 特徴的な構造を持つ。このように、物質や宇宙も多元要素からなる自己組織系とみなすことができる。 我々の研究テーマは、生物・物質・宇宙にまたがる物理学上の難問を、自己組織系として統一的に捕らえ、その普遍的な理解 と新しい学問分野の創造を目指すものである。 このような研究は、細分化された個々の分野の中に閉じこもっていては遂行不可能である。 広い視野で異分野を眺めつつ、新しい学問の芽を創造することが必要である。そのためには、異分野間の共同研究による 相乗効果によって、個々の力では到達できない成果を得るための“システムと場”が必要である。 そこで、研究室間の垣根を撤廃して有機的な共同研究ネットワークを構築し、異分野間での意思疎通と共通の問題意識を明確 にし、共有できる“システムと場”を作り上げる。それが、ここで提案する「自己組織系物理ホリスティック研究所」である。 ホリスティック(holistic)はギリシャ語のホロス(holos=全体)に由来し、「部分を積み重ねても全体にはならない、全体は一つ の有機的なつながりで、部分の和とは異なる」という考え方を意味する。 ここで我々が提案する「ホリスティック研究所」とは、物理学の細分化された分野を個別に学び研究するのではなく、分野間の 有機的つながりを理解し、広い視野から物理学を研究するシステムである。 主な研究活動計画を以下に列挙する (1) 異分野間の共同研究による自己組織系の研究 (2) 専任教員と相補的な能力を持った客員教員の採用 (3) 各種研究会・国際シンポジウムの開催 (4) 大学院生の研究支援 (5) 異分野間の共同研究に基づく大型競争的資金の獲得 ‖研究員‖所 長石渡 信一 (理工学部教授) 研究員 石渡 信一 (理工学部教授) 大谷 光春 (理工学部教授) 堤 正義 (理工学部教授) 相澤 洋二 (理工学部教授) 田崎 秀一 (理工学部教授) 大島 忠平 (理工学部教授) 角田 頼彦 (理工学部教授) 寺崎 一郎 (理工学部教授) 小松 進一 (理工学部教授) 鵜飼 一彦 (理工学部教授) 中島 啓幾 (理工学部教授) 橋本 周司 (理工学部教授) 久村 富持 (理工学部教授) 竹内 淳 (理工学部教授) 千葉 明夫 (理工学部教授) 大場 一郎 (理工学部教授) 中里 弘道 (理工学部教授) 栗原 進 (理工学部教授) 勝藤 拓郎 (理工学部助教授) 船津 高志 (理工学部教授) 上江洲 由晃 (理工学部教授) 大師堂 経明 (理工学部教授) 前田 惠一 (理工学部教授) 山田 章一 (理工学部助教授) 山崎 義弘 (理工学部専任講師) 鷹野 正利 (理工学総合研究センター助教授) 菊地 順 (理工学総合研究センター教授) 長谷部 信行 (理工学総合研究センター教授) 鷲尾 方一 (理工学総合研究センター教授) 濱 義昌 (理工学総合研究センター教授) 輪湖 博 (社会科学部教授) ‖関連リンク‖◎早稲田大学総合研究機構http://www.waseda.ac.jp/kikou/
|
||||||||||||